淡海乃海〜水面が揺れる時〜
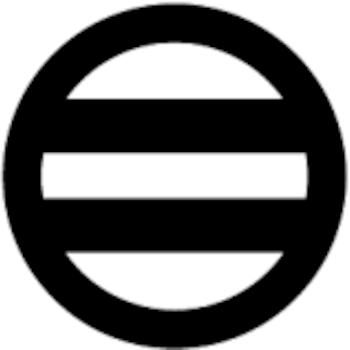 足利 義昭
足利 義昭
足利幕府最後の将軍。
ただ史実と異なり、淡海世界では結構悲惨な最後を迎えてしまった。
たぶん最後まで自分の境遇には不満だったんでしょうねぇ。
将軍職に拘らずに生きていければそれなりに幸せになれただろうに、とは思うけれど、この方にとっては一族及び自身の存在証明になってしまっていたみたいだからね。。。
なんかねー。
一番悪いのは幕臣だと思う!
三渕さんなんて頭良いんだから、もっと本当に将軍家の為を考えて諫言もきっちりすべきだったんじゃない?!
(弟と張り合ってる場合じゃないヨー)
史実では...
天文6年(1537年)11月13日、第12代将軍・足利義晴の次男として、京都で誕生。
幼名は千歳丸。
室町幕府の第15代(最後の)征夷大将軍(在職:1568年〈永禄11年〉- 1588年〈天正16年〉)。
足利将軍家の家督相続者以外の子息として、慣例により仏門に入って、覚慶(かくけい)と名乗り、一乗院門跡となった。
兄・義輝が永禄の変で三好三人衆らに殺害されると、細川藤孝ら幕臣の援助を受けて南都から脱出し、還俗して義秋(よしあき)と名乗る。その後、朝倉義景の庇護を受け、義昭に改名した。
織田信長に擁されて上洛し、第15代将軍に就任した。その後、信長と対立。
やがて京都から追われ、一般にはこれをもって室町幕府の滅亡とされている。
義昭は京都追放後も将軍として活動を続けており、河内国や和泉国、紀伊国に滞在したのち、備後国へ下向した。そして、毛利輝元の庇護を受け、亡命政権・鞆幕府を樹立し、信長に対抗した。
信長が本能寺の変によって横死したのち、豊臣政権が確立すると帰京し、豊臣秀吉から山城国槙島に1万石の所領を認められた。そして、将軍を辞して出家し、昌山道休(しょうざん どうきゅう)と号した。
義昭は前将軍であったので、殿中での待遇は大大名以上であり、また秀吉の御伽衆に加えられるなど、貴人として遇された余生を送った。